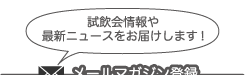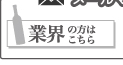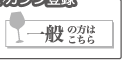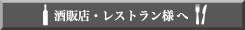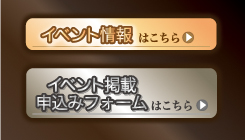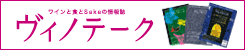今、注目のワイン産地を識る Vol.3
アメリカ大陸、日本編

ワイン産地として実は古い歴史をもちながら、しかし、その高いポテンシャルにふさわしい知名度を獲得していない国や地域にスポットをあてる、ワインコンプレックス「いま注目のワイン産地を識る」企画。
第3回はアメリカ大陸編に加え、特別企画として、ワインスペシャリストとして活躍する遠藤利三郎氏に、日本ワインの「今」がわかる日本編を語っていただいた。
アメリカ大陸編
チリ(Chile)
長い国土にさまざまなテロワールが個性豊かなチリ

チリでワイン造りがはじまったのは16世紀半ば。スペイン人の入植とともにぶどうが持ち込まれ、ほとんど同時期にワインが造りはじめられた。19世紀半ば頃には、フランス系品種が大量に持ち込まれるなどの発展があった。
大きな変化を見せたのは1980年代のこと。70年代後半頃から、海外の造り手がチリのテロワールに注目。ステンレスタンクで、温度を管理しながら発酵・熟成を見守る近代的醸造技術の導入によって、フルーティーで口あたりの良いワインが多く造られた。瞬く間にチリワインは、世界市場において「安くて美味しい」というイメージを獲得したのである。
2000年以降は、プレミアムワイン造りがさかんになっている。シャルドネやカベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、シラーズといった国際品種が多く、ことにチリらしい味わいが表現される品種といえば、白はソーヴィニヨン・ブラン、赤はカルメネールのイメージが強い。
チリの主要産地は、北からコキンボ、アコンカグア、セントラル・ヴァレー、スール、セカノ・インテリオル、アウストラルの各地方がある。ことに、霧の侵入によって繊細な果実が育まれるエルキ・ヴァレー、良質な石灰質土壌で知られるリマリ・ヴァレー、極めて冷涼なチョアパ・ヴァレーを含むコキンボ地方は、近年注目の産地。ソーヴィニヨン・ブラン、シャルドネ、ピノ・ノワール、カベルネ・ソーヴィニヨンなどが、ミクロクリマを活かしながら栽培されている。
アコンカグア地方は、アコンカグア・ヴァレー、カサブランカ・ヴァレー、サン・アントニオ・ヴァレーを含む。セントラル・ヴァレー地方は、マイポ・ヴァレー、ラペル・ヴァレー、カチャポアル・ヴァレー、コルチャグア・ヴァレー、クリコ・ヴァレー、マウレ・ヴァレーを含む。スール地方は、イタタ・ヴァレー、ビオビオ・ヴァレー、マジェコ・ヴァレーを含む。他に、クリコ、マウレ、ビオビオ、イタタの非灌漑畑で栽培されたパイスとサンソーに適用されるD.Oセカノ・インテリオル、スールよりさらに南に認定されたD.Oアウストラルがある。
チリには、カトリカ大学やチリ大学など、世界的にも高い水準をもつ農業工学部や醸造学部を有する大学が数多くある。最高学府といわれるカトリカ大学は、世界に26あるヴァチカン直轄の大学で、農業工学を5年間修めた後、修士課程で醸造を学ぶ厳格なカリキュラム。また各地に観測所を設ける取り組みなどで知られるチリ大学は、気象学のエキスパートを養成する専門機関として、世界的にも知られている。今、チリワインの最前線で活躍しているのが、これらの学府で学んだ、チリ出身の醸造家たちである。
チリは、ワソという誇り高きカウボーイで知られた国。また、かつてチリを訪れたイギリス軍人ジョン・バイロン(1723 〜 1786)は、「チリ人ほど巧妙な馬の乗り手は世界でも見たことがない。彼らは100歩離れたところにあるものをとりにゆく時にも、馬を使う」と、感心したとか。その子孫であるチリ出身の若き醸造家たちが、車やモトクロスで身軽に国中をめぐり、優れた畑やぶどう品種を掘り起こし、次々と新たなミクロクリマを発見している。
アルゼンチン(Argentina)
安定のワイン産地アルゼンチン。近年の注目はパタゴニア
近代的醸造にもいち早く取り組んでいる。1816年にスペインから独立、1850年代には、カベルネ・ソーヴィニヨンやセミヨンなどの品種がフランスから持ち込まれた。この中に、後にアルゼンチンにおいて大をなすマルベックも含まれていた。1885年には、ワインの主要産地メンドーサと主都ブエノスアイレスを結ぶ鉄道が開通。1902年にはアルゼンチン最初の醸造学校が、メンドーサに開校している。
2016年現在、アルゼンチンは世界第9位のワイン生産国にして、消費量は世界第8位。このことからもわかるように、極めて自国消費率が高い国である。しかし90年代以降、旧世界の著名な醸造コンサルタントが続々と参入し、世界市場で高い評価を獲得し得る輸出アイテムの充実が図られた。主要産地は、サルタ、カタマルカ、トゥクマンの各州を含む北部地方、メンドーサ、サン・ファン、ラ・リオハの各州を含むクージョ地方、南部のパタゴニア地方がある。
北部地方とクージョ地方のワイン産地は、標高4000 〜 7000メートルのアンデス山脈の麓、国土の西側に点々と展開している。標高は高く、最高地点は3000メートルを超す。乾燥し、昼夜寒暖差が大きく、必要な水分は多くの場合清冽なアンデス山脈の伏流水で補われる。代表品種はマルベック。本来は南仏系の品種だが、アルゼンチンのテロワールで育むと、力強く繊細で、ストラクチャーに優れた赤ワインとなって実力を発揮する。また、花のような芳香をたたえたトロンテスもこの地方ならではの白ワインとなる。
また近年では、アルゼンチン南部のパタゴニア地方にも注目が集まっている。リオ・ネグロ、ネウケン、ラ・パンパの各州を含むこの地方は、標高こそ平均350メートルと低めであるが、夏場の夜間には南極から冷たい風が吹き込み、昼夜寒暖差が極めて大きい。この冷涼な環境を活かして、シャルドネ、セミヨン、トロンテスなどの品種が栽培され、ことにピノ・ノワールの注目度が高い。
ウルグアイ(Uruguay)
タナの魅力を開花させたウルグアイ

ウルグアイでワイン生産がはじまったのは、17世紀半ばといわれている。1516年にスペインの植民地となり、入植してきた人びとによって、ぶどう、オリーブ、クルミなどの栽培がはじめられた。当時、ぶどうから造られていたワインは、もっぱら自家消費用であった。
商業的ワイン生産がさかんになったのは、1828年に独立して以降のこと。1870年代になると、フランスなどから醸造に適した品種のぶどうが持ち込まれるようになった。現在、ウルグアイを代表する赤系品種となっているタナも、この頃に伝来したと考えられている。
ウルグアイが位置している南緯30〜35度の地域は、夏場の気候的特徴として、昼間に気温が上昇し、夜間に急激に冷え込む傾向がある。ぶどうは、日中の温かさで糖を蓄え、夜間の冷え込みによって酸を蓄える。つまり、ワイン用ぶどうの生育には理想的環境である。
ウルグアイの主要産地は、首都のあるモンテビデオ、南部のカネローネス、南西部に位置し世界遺産コロニア・デ・サクラメントを有するコロニア、西部のサルト、北東部のリベラなど。現在、国全体のぶどうの作付面積は約9000ヘクタールにのぼり、およそ350のワイナリーがあるという。
白系のソーヴィニヨン・ブラン、シャルドネ、赤系のカベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、マルベックなどがあるが、主要品種はなんといっても赤系品種のタナが国を代表するぶどうといえよう。
1990年代以降は、投資や技術導入などによって大きな品質向上がみられ、ウルグアイワインは世界のワインコンテストにおいて、さまざまな賞を獲得した。現在では、アメリカやヨーロッパ諸国、ロシア、東欧、北欧などに意欲的に輸出され、好評を得ている。
ブラジル(Brazil)
食用ぶどうの産地ブラジルに秘められたポテンシャル

ブラジルでぶどう栽培がはじまったのは、1532年のこと。ポルトガル人によって、サンパウロ州に植樹されたのが始まりという。その後、17世紀初頭には布教活動を行うイエズス会によってリオグランデ・ド・スル州へと広められ、また18世紀にはマデイラ諸島とアゾレス諸島からやってきた開拓者がリオグランデ南岸にイザベラという品種を持ち込んだという。1870年代には、セラ・ガウチャのイタリア系移民によって、イタリア系のぶどう品種によって、ワイン造りが行われていたことが知られている。
近代的なワイン生産がさかんになるのは、1970年代頃からのこと。現在では、およそ150のワイン醸造所が存在しているという。
ブラジルは、ドイツ、ギリシャに続く世界17位のぶどう生産国だが、その大半は食用である。ワインが造られているのは国土の南部、ウルグアイとアルゼンチンに近いリオグランデ・ド・スル州がほとんど。南半球に位置するブラジルでは、南へ行くほど気候は冷涼になるのだ。
わずかに、サンタカタリーナ、ミナス、サンパウロの各州でワインの生産が見られるが、世界市場で目にすることができるのは、リオグランデ・ド・スル州の中でも、より標高が高く冷涼なセラ・ガウチャ地域のワインであるという。
国際品種のぶどうが用いられることが多く、白系品種は、ソーヴィニヨン・ブラン、シャルドネ、リースリング、ゲヴュルツトラミネールなどのほかマスカットも。赤系品種は、タナ、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、メルロー、ピノ・ノワール、マルベックなど。
また、モエ・エ・シャンドン社がブラジルで高品質なスパークリングワインを造っていることからもうかがえるように、ブラジルの人びとはスパークリングワインへの嗜好性が高い。
メキシコ(Mexico)
カリフォルニアワインの原点となった、メキシコ、バハ・カリフォルニアワイン

メキシコというと、テキーラやビールのイメージが濃厚だが、まさにこの地こそ、知られざる、そして、実はアメリカ大陸の中でも屈指のワイン産地である。ワインが造られているのは、アメリカ合衆国カリフォルニア州に隣接する、バハ・カリフォルニア半島である。
そもそもカリフォルニア一帯におけるぶどう栽培の歴史は、現在ではメキシコ領となっているバハ・カリフォルニアからはじまり、現アメリカ合衆国領となっているカリフォルニア州へと及んでいったのである。
しかしバハ・カリフォルニアでは長くワインの停滞期が続き、近代的なワイン生産がはじまったのは今世紀初頭だ。
元来ぶどうは乾いた気候を好む植物だが、バハ・カリフォルニアの年間降雨量は300ミリリットル以下。それも雨季である11月から3月の間しか降らないという環境では、灌漑が必要になる。しかし、この半島にはそれほど大きな川がない――そうした諸々の要因で、ワインは産業としては伸び悩んでいたのである。
しかし、降雨量の少なさは、逆手に取ればワインにとっては長所となる。現在では、地下水の利用などで灌漑をまかない、ぶどう栽培に適した地中海性気候を活かして、エレガントなワイン造りを実現させている。まるで、ヨーロッパ北部地域を髣髴とさせるような、繊細華麗なアイテムも多く、アメリカやカナダでは、バハ・カリフォルニアは、ワイン産地としてよく知られた土地である。
メキシコでワインが造られているのは、バハ・カリフォルニア半島の北部、ノルテ州バジェ・デ・グアダルーペ・ヴァレー近郊、サン・ビセンテ、セント・トマスなどの地域である。
白系品種は、ソーヴィニヨン・ブラン、セミヨン、ヴィオニエ、シャルドネなど。赤系品種は、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、シラー、プティ・シラー、テンプラリーニョ、ジンファンデル、グルナッシュ、カベルネ・フラン、ネビオロなど。ことに、フュメ・ブランと呼ばれるソーヴィニヨン・ブランとプティ・シラーには、バハ・カリフォルニアならではの品格が備わる。
日本編
日本(Japan)
スペシャルインタビュー
みんなで産地を育てる模索の時期。最高に面白い日本ワイン

「日本ワインは今、最高に面白い時期にある!」と語るのは、日本ワインを愛する会の副会長もつとめておられるワインスペシャリスト遠藤利三郎氏。
「ことに、北海道は注目産地。余市や函館では、素晴らしいクオリティのワインが続々と造られています。そもそも台風が来ないなどの気候条件をもつ北海道は、ぶどうの生育には最適。ひと昔前は、やや冷涼すぎる傾向もありましたが、今ではぶどうの生育に向いた冷涼さとして、ワイン造りに有効な条件となっています」
さらに伸びしろとして重要なのは、その「広さ」だという。
「土地が広いということは、広大な一枚畑ができるということ。本州に比べると、土地も安いですしね。日本のぶどう畑の多くは、小さな畑があちこちに点在しているケースが多いでしょう? 移動するだけでも造り手には大きな負担。それに比べると、北海道の畑は作業効率が良く、かなり思い切った機械化にも取り組むことができる。北海道は、質量ともに現実的に海外のワインに対抗でき得る、最有力の日本のワイン産地といえるでしょう」
また、日本ワインは、全国的にも大きな飛躍の可能性を秘めた時期に来ている、と遠藤氏は語る。
「以前…私より上の世代の造り手さんたちが醸造の勉強をしようというと、例えばボルドー大学や、ドイツのガイゼンハイム大学に学ぶしかなかった。赤ワインはタンニンたっぷりの長期熟成タイプ、白ワインは甘みを残して爽やかに─という具合に、お手本の視野が狭かった。また、消費者も、他は知らずにそういうワインを求めていた。ある意味テロワールなどとは関係なく、お手本に従い、求められるワインが造られていたわけです」
変化のきっかけは、1990年代後半の赤ワインブームだという。
「スーパーマーケットやコンビニエンスストアで、世界中のさまざまなワインが手に入るようになりました。その時に20代だった人が、今は40代になっている。日本の消費者のワインに対する考え方も、ずいぶん変わってきました。今では造り手は、世界中のありとあらゆるワインをお手本として、自分の畑のテロワールの特徴を活かそうとするようになっている。そうしたバラエティー豊かなワインが、日本のあちこちで造られはじめています」
テロワールを語ることができる時代になりつつある─というのが日本ワインの現状らしい。
「とはいえ、まだまだ模索の時期。テロワールとぶどう品種がピタリとあてはまった成功事例は、例えば勝沼の甲州種や塩尻のメルローなどごくわずか。面ではなく、点に過ぎません。造り手さんたちは、テロワールの見極めや品種の個性を模索し、試行錯誤の真っ最中なのです。テロワールと品種が見事に結びつき、『これは大成功だ!』といえる事例が全国で見られるようになるまでには、まだ5年や10年はかかるでしょう」
だからこそ今、すべての人にとって、「日本ワインは、最高に面白い」のだそうだ。
「ワイン造りのプロに対して、素人が何かいうのは失礼なのでは? なんて尻込みをする人がいますが、そんなことはありません。一般の消費者こそ、もっと声をあげていい。実は造り手は、消費者の声を待っている。『この土地の、この品種はいい!』とか『これはいまひとつだ』というリアルな声が聞きたいのです。消費者に買ってもらえなければ、ワインを造る意味がないのですから。そういう意味では、“産地の個性は、ワインを飲む人の声によって作られていく”といって過言ではありません。ソムリエという職業は、造り手と消費者を繋ぐのが仕事。やはり一緒に産地を作っているわけです」
「このワインが美味しい!」という消費者の声が評判を呼び、それが成功事例となって、産地の個性が形成されていく。
「私は、日本ワインの応援をしていてつくづく、素晴らしくラッキーな時代にめぐり合わせたものだと感謝しています。日本の各地域の産地が育っている真っ最中だからこそ、その育成に自分自身が関わることができる。みんなで日本ワインを育てているというリアルな喜びが感じられるなどというめぐり合わせは、滅多にあるものではないですよ。」
 お話をうかがったのは三代目 遠藤利三郎氏。
お話をうかがったのは三代目 遠藤利三郎氏。
遠藤利三郎商店オーナー。ワインビストロ、ワインレストランを多数経営する傍ら、日本輸入ワイン協会事務局長、日本ワインを愛する会副会長をつとめるなど、幅広く活躍。豊富な知識を駆使したワインエデュケーションには、定評がある。
※当サイトの内容、画像等の無断転載、無断使用を固く禁じます。